概要
2025年8月12日、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、応用情報技術者試験、高度試験、情報処理安全確保支援士試験を2026年度からCBT(Computer Based Testing)方式へ移行することを発表しました。これまでペーパー方式で実施されてきたレベル3以上の試験がデジタル化され、受験者にとって大きな転換点となります。
主な変更点
実施方式の全面的なデジタル化
- 対象試験:レベル3以上の全10試験区分
- 実施時期:2026年度から
- 解答方法:記述式・論述式問題もキーボード入力で解答
試験日程の柔軟化
従来の固定日程から大きく変わります:
- 従来:春期(4月)・秋期(10月)の年2回、各1日のみ
- 新方式:一定期間内の複数日から選択可能
- 予約制:会場ごとの予約枠から自由に日時を選択
科目名称の変更
時間帯の概念がなくなることに伴い、科目名が変更されます:
| 現在の名称 | CBT移行後の名称 |
|---|---|
| 午前試験 | 科目A試験 |
| 午前Ⅰ試験 | 科目A-1試験 |
| 午前Ⅱ試験 | 科目A-2試験 |
| 午後試験 | 科目B試験 |
| 午後Ⅰ試験 | 科目B-1試験 |
| 午後Ⅱ試験 | 科目B-2試験 |
変更されない要素
以下の要素は従来通り維持されます:
- 試験で問う知識・技能の範囲
- 出題形式(多肢選択式・記述式・論述式)
- 出題数
- 各科目の試験時間
CBT化がもたらすメリット
1. 受験者の負担軽減
キーボード入力により、以下の点で負担が軽減されます:
- 文章の挿入・削除が容易
- 書き直しの手間が大幅に削減
- 手書きによる疲労の軽減
2. 受験機会の拡大と利便性向上
- 複数の日程から都合の良い日を選択可能
- 会場ごとの時間帯から選択可能
- 仕事や学業との両立がしやすくなる
3. 時間を気にしない受験環境
午前・午後という時間帯の概念から解放されることで、受験者は自分の最適なコンディションで試験に臨めるようになります。早朝型の人も夜型の人も、それぞれのベストな時間帯での受験が可能になる可能性があります。
4. 現代の出題形式との相性
近年の情報処理技術者試験では、文字数制限なしの記述問題も出題されています。このような問題形式において、CBT方式は以下の点で優れています:
- 文字数を気にせず思考に集中:手書きと異なり、文字数のカウントが容易
- 推敲の自由度向上:構成を考えながら、自由に文章を組み替え可能
- 読みやすさの確保:採点者にとっても判読性の問題がなくなる
- 時間効率の改善:タイピングに慣れた受験者にとっては、手書きより高速に解答可能
5. 手続きのデジタル化への期待
すでにCBT化されている基本情報技術者試験や情報セキュリティマネジメント試験では、以下のデジタル化が実現されています:
- 紙の受験票の廃止:受験票の郵送や持参が不要
- 本人確認の簡素化:顔写真付き身分証明書のみで受験可能
- オンラインでの成績照会:受験者マイページで合否確認が可能
一方、現在の応用情報技術者試験や高度試験では:
- 紙の受験票が郵送で届く
- 受験票を紛失すると合格証書が届くまで合否が分からない
- 証明写真の貼付が必要
2026年度のCBT化により、応用情報技術者試験以上の試験でも手続きのデジタル化が進むことが期待されます。特に、紙の受験票による煩雑さや紛失リスクから解放されることは、受験者にとって大きなメリットとなるでしょう。
個人的な所感
この改革は、IT業界で働く人々にとって非常に理にかなった変更だと感じます。特に以下の点が評価できます:
メリットとして評価できる点
- デジタルネイティブ世代への対応:キーボード入力が当たり前の世代にとって、手書きよりもむしろ自然な解答方法
- 実務との親和性:実際の業務ではドキュメント作成もコーディングもすべてキーボードで行うため、試験環境が実務環境に近づく
- 柔軟な受験計画:プロジェクトの繁忙期を避けて受験日を選べることで、キャリア形成と業務の両立が容易に
- 論述問題との相性の良さ:特に高度試験の論文では、構成の組み替えや推敲が重要であり、CBT化によってより質の高い解答が期待できる
- 手続きの効率化:基本情報技術者試験等で実現しているデジタル化が高度試験にも拡大されることで、受験手続き全体がスマートに
論文系試験への大きなインパクト
「論文系の試験が一番影響が大きそう」
CBT化の恩恵を最も受けるのは、間違いなく論文(論述式)問題を含む試験でしょう。具体的には:
- ITストラテジスト試験
- システムアーキテクト試験
- プロジェクトマネージャ試験
- ITサービスマネージャ試験
- システム監査技術者試験
これらの試験では、2,000字~3,000字程度の論文を手書きで作成する必要がありました。CBT化により:
- 構成の大幅な変更が容易に:手書きでは困難だった段落の入れ替えや、論理展開の修正が簡単に
- 推敲時間の確保:書き直しの物理的な時間が削減され、内容の検討により多くの時間を割ける
- 文字数管理の効率化:リアルタイムで文字数が把握でき、バランスの良い論文構成が可能
- 読みやすさの向上:手書きの癖や疲労による文字の乱れがなくなり、採点者にとっても評価しやすく
特に、論文試験では「時間との戦い」という側面が強く、手書きの速度が合否を左右することもありました。CBT化により、純粋に論理的思考力と知識・経験が評価される試験になることが期待されます。
競争環境についての現実的な視点
ただし、以下の点は冷静に認識しておく必要があります:
「結局、受験がやりやすくなったとしても、それは全員同じ条件なので、合格率のレンジに入るように努力が必要なのは変わらない」
CBT化により受験環境は改善されますが、試験の難易度や合格基準は変わりません。むしろ、受験しやすくなることで競争が激化する可能性もあります。本質的には、しっかりとした知識・技能を身につけることが合格への道であることに変わりはありません。
受験率への影響予測
「CBT化により受験率は上がりそう(いわゆる申込だけして受験しない人は大幅に減りそう)」
従来の試験では、申込後に仕事の都合がつかなくなったり、準備不足を理由に欠席する受験者が一定数存在していました。CBT化により:
- 直前まで日程変更が可能になるため、仕事の都合での欠席が減少
- 自分のペースで準備が整ってから受験できるため、準備不足での欠席も減少
- 結果として、申込者に対する実際の受験者の割合(受験率)が向上
これは、真剣に資格取得を目指す受験者にとっては、より実力が正当に評価される環境になることを意味します。
まとめ
2026年度から始まる情報処理技術者試験のCBT化は、単なるデジタル化以上の意味を持つ改革です。受験者の利便性向上はもちろん、より実務に即した形での知識・技能の評価が可能になり、真に実力のあるIT人材の発掘・育成につながることが期待されます。
特に、以下の3つの観点から、この改革は大きな意義を持ちます:
- 文字数制限なしの記述問題や論述問題において、CBT方式の恩恵は大きく、受験者がより本質的な内容に集中できる環境が整う
- 手続きのデジタル化により、紙の受験票による様々な問題から解放され、スマートな受験体験が実現する
- 受験環境は改善されるが、競争の本質は変わらず、むしろ受験率の向上により、より実力が問われる試験になる
今後の詳細な実施要項の発表が待たれますが、この改革が日本のIT人材育成とDX推進の加速に大きく貢献することは間違いないでしょう。受験者としては、この変化をチャンスと捉え、しっかりとした準備で臨むことが重要です。
参考:IPA プレスリリース(2025年8月12日)
https://www.ipa.go.jp/pressrelease/2025/press20250812.html


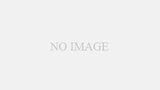

コメント